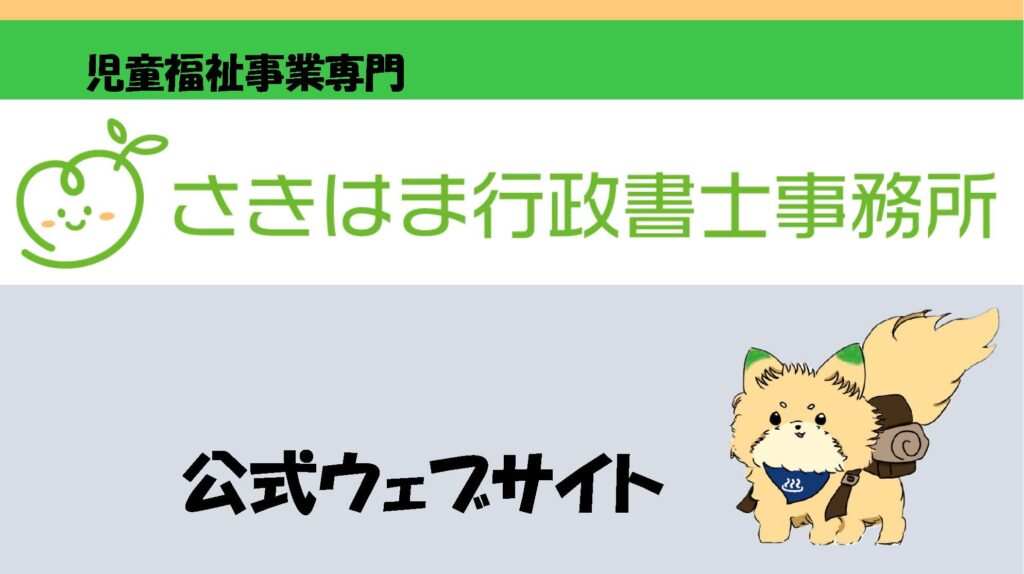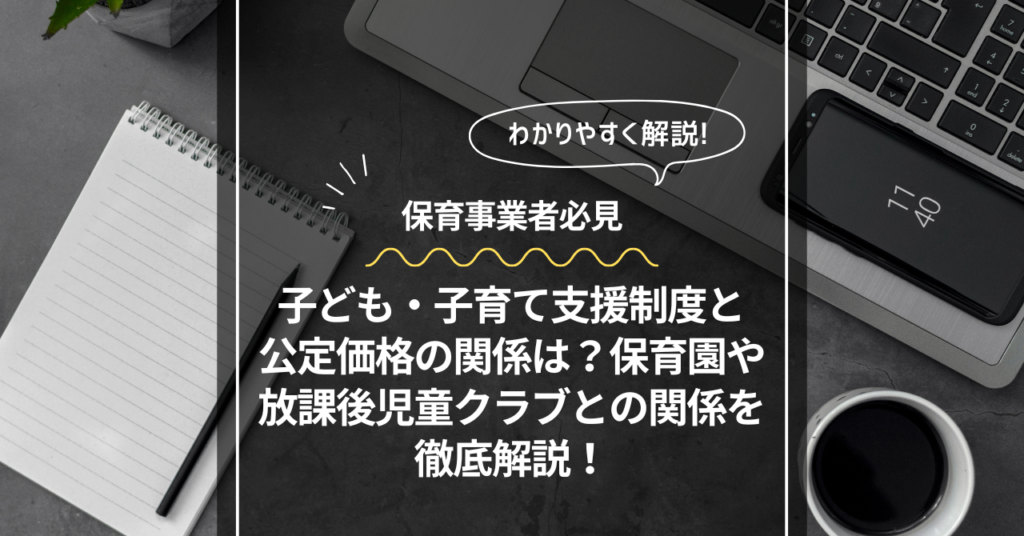
子ども・子育て支援制度は量と質の両面から子育てを社会全体で支えるために創設された制度です。この制度によって保育園や幼稚園にどのようなメリットがあるのか?放課後児童クラブと本制度の関係は?子ども・子育て支援制度における疑問を徹底解説します。
子ども・子育て支援制度とは?
「子ども・子育て支援制度」とは、平成24年8月に成立した「子ども・子育て支援法」、「認定こども園法の一部改正」、「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の子ども・子育て関連3法に基づく制度のことをいいます。
事業者や利用者にとって身近な市町村が中心となって運用されているのが特徴です。国や都道府県は制度面や財政面の支援を通して本制度に関わっています。
また企業による子育て支援をバックアップする機能も備えています。
制度の概要
| 現物給付 | 市町村主体 | 国主体 | ||
| 子どものための教育・保育給付 | 子育てのための施設等利用給付 | 地域子ども・子育て支援事業 | 仕事・子育て 両立支援事業 |
|
| 認定こども園・幼稚園・保育所・ 小規模保育等に係る共通の財政支援 【施設型給付費】 ・幼保連携型 ・幼稚園型 ・保育所型 ・地域裁量型 【地域型保育給付費】 ・小規模保育 ・家庭的保育 ・居宅訪問型保育 ・事業所内保育 | 施設型給付を受けない幼稚園、 認可外保育施設、預かり保育事 業等の利用に係る支援 【施設等利用費】 ・施設型給付費を受けない幼稚園 ・特別支援学校 ・預かり保育事業 ・認可外保育施設 ※一時預かり事業・病児保育事業・子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業) 認定こども園(国立・公立大学 法人立)も対象 | 地域の実情に応じた子育て支援 ①利用者支援事業 ②延長保育事業 ③実費徴収に係る補足給付を 行う事業 ④多様な事業者の参入促進・ 能力活用事業 ⑤放課後児童健全育成事業 ⑥子育て短期支援事業 ⑦乳児家庭全戸訪問事業 ⑧・養育支援訪問事業 ・子どもを守る地域ネット ワーク機能強化事業 ⑨地域子育て支援拠点事業 ⑩一時預かり事業 ⑪病児保育事業 ⑫子育て援助活動支援事業 (ファミリー・サポート・ センター事業) ⑬妊婦健診 | 仕事と子育ての両立支援 ・企業主導型保育事業 ⇒ 事業所内保育を主軸とした 企業主導型の多様な就労形態に対応した 保育サービスの拡大を支援 (整備費、運営費の助成) ・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業 ⇒ 繁忙期の残業や夜勤等の 多様な働き方をしている労働者が、 低廉な価格でベビーシッター 派遣サービスを利用できるよう支援 ・中小企業子ども・子育て支援環境整備事業 ⇒くるみん認定を活用し、 育児休業等取得に積極的に取り組む 中小企業を支援 |
|
| 現金給付 | 【児童手当交付金】0~3歳未満15,000円 3歳~小学校修了まで第1子・第2子:10,000円第3子以降:15,000円 中学校10,000円 所得制限限度額(960万円)~所得上限額(1,200万円)5,000円(特例給付) |
|||
子ども・子育て関連3法の主な目的
「子ども・子育て支援法」、「認定こども園法の一部改正」、「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の主な目的として挙げられるのは下記のとおりです。
認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付
地域型保育給付は、都市部における待機児童解消とともに、子どもの数が減少傾向にある地域における保育機能の確保に対応しています。
認定こども園制度の改善(幼保連携型認定こども園の改善等)
幼保連携型認定こども園について、認可・指導監督を一本化し、学校及び児童福祉施設としての法的に位置づけています。
認定こども園の財政措置を「施設型給付」に一本化しました。
地域の実情に応じた子ども・子育て支援
利用者支援、地域子育て支援拠点、放課後児童クラブなどの「地域子ども・子育て支援事業」の充実。教育・保育施設を利用する子どもの家庭だけでなく、在宅の子育て家庭を含むすべての家庭及び子どもを対象とする事業として、市町村が地域の実情に応じて実施していきます。
基礎自治体(市町村)が実施主体
市町村は地域のニーズに基づき計画を策定、給付・事業を実施します。
国・都道府県は実施主体の市町村を重層的に支えます。
社会全体による費用負担
消費税率の引き上げによる、国及び地方の恒久財源の確保を前提としています。
(幼児教育・保育・子育て支援の質・量の拡充を図るためには、消費税率の引き上げにより確保する0.7兆円程度を含めて1兆円超程度の追加財源が必要となります)
政府の推進体制
制度ごとにバラバラな政府の推進体制を整備。内閣府に子ども・子育て本部が設置されました。
子ども・子育て会議の設置
有識者、地方公共団体、事業主代表・労働者代表、子育て当事者、子育て支援当事者等(子ども・子育て支援に関する事業に従事する者)が、子育て支援の政策プロセスなどに参画・関与することができる仕組みとして、国に子ども・子育て会議を設置しました。
市町村等の合議制機関(地方版子ども・子育て会議)の設置努力義務としています。
保育園・幼稚園と子ども・子育て支援制度の関係
本制度によって保育士や幼稚園教諭等に対する処遇改善加算を行われます。職員への報酬が向上する事で人材の定着・新規採用・能力開発の促進が図られます。
処遇改善加算に関する詳細は別記事にて詳細に解説しているので、そちらをご覧ください。
放課後児童クラブと子ども・子育て支援制度の関係
子ども・子育て支援制度は地域の子育て支援の充実が目的となっています。その一環として放課後児童クラブの運営がされています。放課後児童クラブとは保護者が昼間家庭にいない児童(小学生)が、放課後に小学校の余裕教室、児童館などで過ごすことができる取組みです。
「放課後児童クラブ運営指針」を策定し、質の向上を図っています。また、職員の処遇改善を行い、職場への定着及び質の高い人材の確保をすることでも質の向上が図られています。
「放課後子ども総合プラン」に基づき放課後児童クラブの設置拡充を行っています。「放課後子ども総合プラン」では小1の壁を打破し、次代を担う人材の育成を目指しています。
制度に大きく関わってくる「公定価格」とは?
子ども・子育て支援新制度における公定価格は、教育・保育に必要な費用の金額を指します。これは、国が定めた基準に基づいて算定され、子ども一人当たりの単価として設定されます。
この基準には、「認定区分(1号認定、2号認定、3号認定)」、「保育必要量」、「施設の所在する地域(地域区分)」などが含まれ、子どもの年齢や施設の定員によっても子ども一人当たりの単価が異なります。
施設利用希望者に必要となる「認定」とは?
保育認定は、保育の必要性を市町村が認定する制度です。この認定によって、保育園やこども園などの保育施設を利用する際の保育料やサービスが決まります。認定区分は1号・2号・3号の三種に分類されています。
例えば保育を必要とする事由に該当しないと判定されたならば「1号」認定を受けることになります。この場合は、幼稚園や認定こども園が利用できます。
行政書士へのお問い合わせはこちら
さきはま行政書士事務所では「子どもの笑顔が輝く街づくり、私たちがサポートします」をモットーに保育園や児童福祉事業の運営サポートを行っています。LINEやメールフォームで気軽に問い合わせることができます。詳しくは公式サイトをご覧ください。